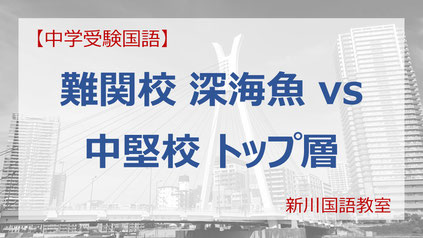
「中学受験『難関校で中位以下』と『中堅校で成績がトップ』はどちらが大学受験に有利?」という記事がありました。最近は「難関校で成績が下位の“深海魚”になるより、中堅校のトップ層にいる方がよい」という見方が多い。「それなら中堅校で成績がトップの方が大学受験に有利か?」と問われると単純に「イエス」とは言えない、とのことです。
記事では、難関校のメリットとして次の点があげられていました。
・思考力と探究心のある子どもが多く集まり、互いに良い刺激を受ける。
・難関校に所属している意識が、有能感とモチベーションアップにつながる。
・出身者に社会的立場の高い人が多く、良い人脈に恵まれる。
大学入試は(学校内順位ではなく)全国順位で考えるべきなので「井の中の蛙」にならない方がよい、というご意見です。
これらは最近よく耳にする議論ですが、そもそも「難関校」「中堅校」はどこを想定しているのでしょうか。例えば難関校=開成だとして、(最上位層以外の)併願先で多い本郷・芝を想定しましょう。東大+国公立医学部(除く防医)の合格者は、開成が約200名(学年400名)、本郷が約30名(学年280名)、芝が約20名(学年280名)ですから、開成の深海魚が本郷・芝でトップ層になれる可能性は低そうです。本郷・芝より易しい中堅校では、開成と迷うこと自体がレアなので、意味のない議論のように思えます。
この「鶏口となるも牛後となるなかれ」論争は、繰上げ合格についてもあります。豊島岡のウェブサイトには、次のように書かれていました。
「入学してからの学業成績は必ずしも入試の成績に比例するものではありません。大切なのは本人の満足度と姿勢です。繰上げ合格でもまったく心配はありません。」
入学後の成績はその後の努力次第なので、注意すべきは性格・精神年齢かもしれません。同じ発達段階の仲間に囲まれた方が、長い目で見てメリットが大きいと感じています。
(「続・『二月の勝者』に見る繰上げ合格」をご参照ください。)
