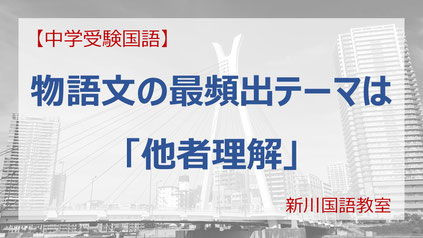
東大合格実績を大きく伸ばして話題の洗足学園ですが、国語科の先生の対談記事がありました。「東大コースのようなものをつくって集中的に勉強させているわけではない」とのこと。とはいえ、きめ細やかな学習支援から、少なくとも学習面では「管理型」という評価が定着しています。
(「東大合格女子校ランキング」をご参照ください。)
対談の中では、
・国語こそ文系・理系すべてのベースになる教科
・国語の物語文は、自分と近い立場の登場人物に感情移入できるかどうかではなく、自分とは全く別次元の世界に生きている人物であっても、あくまで冷静に客観的に分析する力が重要
とありました。塾の教材でも、「自分と近い立場の登場人物」は5年生の前期まで。5年生の後期から「自分とは全く別次元の世界に生きている人物」が出てきて、急に難しくなるのです。
(「5年生の後期は国語の難易度も急上昇①」をご参照ください。)
具体例として、2025年の東大現代文における佐多稲子の短編「狭い庭」が紹介されていました。この問題は、当ブログでも2回にわたって解説しましたので、詳しくはそちらをご覧ください。国語力を鍛える点においては、中学受験は大学受験にそのままつながっているのです。
(「東大現代文で小説が出た!①」「東大現代文で小説が出た!②」をご参照ください。)
上位校の物語文では、「時代や年齢が異なる」登場人物の心情が問われます。2025年入試で言えば、ラ・サール、本郷、山脇学園などで出題された早見和真さんの「アルプス席の母」が典型です。「母子家庭の母親」の心情が出題されているので、できるだけ多くの入試問題に当たって、「多様な視点から考えられる力」を身につけましょう。
(「【読書メモ】『アルプス席の母』早見和真」をご参照ください。)
